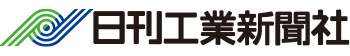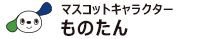セミナー
【ライブ配信セミナー】
BOM・BOPが手間とコストを増やす理由を【原価のプロ】が解説!
強い「生産管理」実現のための原理原則
~「物づくり→紙づくり?」バラバラの部分最適/しわよせで膨大な手作業/経営層はシステム化できていると勘違い~
開催主旨
少し前はDX、昨今は生成AIが大ブームです。
BOM・BOP・ERP…システム導入で理想的な「モノづくり」生産管理体制が作れる!
と言ったようなシステムベンダーの「宣伝文」をよく見かけます。
それでは、デジタル化・システム化でよっぽど現場の生産性が高まっているのか?
その実態はというと…。
むしろ「モノづくり」から「紙づくり」へ?
システム導入で自動化・省力化どころか…伝票手作業入力の手間が膨大に増え、
生産管理担当が疲弊しているという話をよく聞くようになりました。
貴社ではどうでしょうか?
「(期待通り)生産性が上がった!」…という話はほとんど聞こえてきません。
なぜなのか?
どうしてシステム化が当初の「理想通り」に上手く運用できないのか…?
長年、生産管理と原価削減の実務に携わった「原価のプロ」である講師から指摘させていただくと、
理由は大きく二つあります。
理由①ロジックが米国発だから
BOM・BOP・ERPも米国発のシステムで大前提があります。
原則「生産計画変更を受け付けない環境で使うこと」です。
計画変更が頻発する日本の現場で、そのまま使えば、スケジュール・進捗管理がしわ寄せで手作業化するのはむしろ当然の帰結です。
利用②ベンダーがモノづくり素人だから
システムベンダー、行ってしまえばロジックを組んでいる担当者がモノづくりを知らないから。
生産工程・生産管理の経験がない素人が作っているからです。
例えば…
最近は、企画BOMや試作BOM、購買BOMなどは、製品化のステップの中で一部門の業務を支援するためにありますが、この企画BOMや試作BOM、購買BOMなども現物があるわけではありません。
また、会社によっては、必要のない部品表もあります。
特定の部門での業務の効率化には役立ちますが、全体最適には役たちません。
これは、現場を知らない素人がロジックを組むから起きるのです。
モノづくりの大原則は以下の3点です。
①顧客サービスの向上
⇒顧客が欲しいときにすぐに提供できる。
②生産性の向上
⇒生産性を高めることによって、製品のコスト削減を図って行く。
③在庫の削減
⇒必要のない在庫を持たないことによって、資金の有効活用をする。
上記を最適な工程・最適(最小)コストで追求することで「利益獲得」するのが生産管理…BOM・BOP各種システムの存在意義です。
モノづくりについてその目的や意味を理解することなく、BOP・BOMの「理想の姿」を見栄えの良いキレイな図表で説明されても「利益獲得」という目的は達成できません。
この辺りが理解されることないままに、BOM・BOPが導入運用されると…
・バラバラの部分最適
・計画変更のしわ寄せはスケジュール・進捗管理がしわ寄せで手作業化
・経営層は生産管理がシステム化「できてる!」とカン違い
現場の疲弊と不満…不幸の連鎖を生み出すことになります。
ではどうしたらよいのか?
講師は、実務と原理原則に重きを置く「コスト・エンジニア=原価のプロ」です。
昨今のモノづくりでは、現場を見ない、あるいは現場を知ろうとしないコンサルやベンダーによって、新しいモノづくり(生産管理)システムが提唱され、それを信奉する風潮が出ていることに疑問と懸念を感じています(だいたい上手く行かない…)。
こうしたことから、本セミナーを企画いたしました。
BOM・BOPを導入・運用して、「本来実現すべき生産管理」とはどうあるべきか?
そして、理想のモノづくりを実現するために、生産管理システムの核になるBOM/BOP、管理会計について、その重要性や運用の原理原則を解説し、「強い現場の生産管理」実現を目指します。
既にBOM・BOPを導入してもどうも腑に落ちない。
生産性が上がっている気がしない。何かが違う気がする。
あるいは、これからBOM・BOPを導入しようとしているが、どうしたら「強い」生産管理体制を実現できるのか。
悩んでいる方におススメの講座です。ぜひご活用下さい。
概要
| 日時 | 2025年 10月 14日(火) 10:00~17:00 (9:30 ログイン開始)※昼休憩1時間あり |
|---|---|
| 会場 | WEBセミナー WEBセミナーは、WEBミーティングツール「Zoom」を使用して開催いたします。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 ブラウザとインターネット接続環境があれば、どこからでも参加可能です。 |
| 受講料 | お一人様:48,400円(資料含む、消費税込) 受講にあたり |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 申込締切日について | 講座開催の3営業日前17:00〆切 ※セミナーによって締切が異なる場合もございます。早めにお申込みください。 原則、資料を受講者の方へ郵送するため、お手元に届く猶予を頂いております。予めご了承ください。 【営業日】について 営業日は平日になります。 ※土曜/日曜/祝祭日は、休業日です。 (例)6/16(火)開催の場合、6/11(木)が締切日となります。 |
| FAX申込みについて | |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
講師
プログラム
理論編
| 0.BOM・BOP の「理想」と「現実」 |
| 1.BOM/BOPは何のために導入するのか?もう一度目的を確認 |
| ― 生産管理は会社の基幹システム ― 1) モノづくり企業の命題 2) 生産形態と繰返し性(継続性)による生産体制 3) 日本と米国の生産管理の考え方の根本的な違い |
実務編
| 2.「理想的な」生産管理に必要なBOM/BOPの機能・要件を解説 |
| 1) まず生産の用語と意味を正しく理解すること 2) BOM/BOPを正しく定義する ― 意味と役割のズレが問題を生む ― 3) M-BOM(製造部品表)は生産活動の中核である ― 目的別BOMに惑わされない! ― |
| 3.コスト・レビューのためのE-BOM(設計部品表)を使いこなしているか? |
| 1) 製品開発・設計のステップを整理する 2) 生産準備段階でM-BOM(製造部品表)とBOP(工程表)を作る 3) 目標原価の基礎データは現行のM-BOM(製造部品表)とBOP(工程表)から |
| 4.現場で役に立つ生産管理システムの概要とポイント |
| 1) M-BOM(製造部品表)を作ってみよう(事例) 2) なぜ、欲しいときに部品がないのか? ― BOM/BOPと所要量計算、作業スケジュールのロジック ― 3) BOP(工程表)を使って、作業スケジュールを作ってみよう(事例) 4) 見える化できても、リ・スケジューリングは発生する! ― BOP(工程表)と所要時間、作業時間の考え方 ― 5) 生産計画に変更が生じたら何をする!頻繁な変更は? ― 生産計画、BOP(工程表)とSCMの関係 ― |
| 5.強い「生産管理」のためには何が必要か【結論】 |
| 1) 生産計画の期間をどのように決めるのか ― 生産計画、BOP(工程表)、リードタイムのとらえ方 ― 2) 生産管理システムに必要な情報の精度とは 3) BOPとワークセンター(作業区)の整合性について 4) 利益管理とBOM/BOP |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |