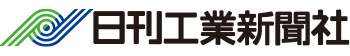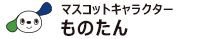セミナー
【ライブ配信セミナー】
どこから手を付ければいいの? 図面のあいまいさをなくす
幾何公差設計法(GD&T)の考え方と実践的使いこなしテクニック
開催主旨
幾何公差は、製品形状の幾何学的特性を表現する公差で、形体の定義からあいまいさをなくす図面記法の1つですが、これを用いた設計手法を、幾何公差設計法(GD&T)と呼びます。
機械部品や製品の設計の現場では、幾何公差を用いた図面表記が一般的になってきましたが、最近よく見聞するのが、幾何公差の定義や使い方を規格書や書籍で学んだあとに、いざ実際に図面を描く段階で、どこから手を付ければいいのか、何を使えばいいのか悩むという声です。
最初から幾何公差を完璧に使いこなすのは難しいかもしれませんが、そもそも部品に対して設計的に求めたい要件は何なのかを考え、それを実現するために必要な指示としてどのような幾何公差を選ぶべきか、という順番で取り組めば理解も深まると思います。
本セミナーでは、幾何公差の特徴と意義を理解し、幾何公差設計法を存分に活用することで、設計意図を正しく伝え、製品品質の向上に役立てるノウハウを習得していただきます。
なお、加工や検査の現場の方にも、設計者の意図を読み解く手がかりとして参考になるでしょう。
進呈書籍
受講特典として、講師著『GD&T(幾何公差設計法)活用術』(日刊工業新聞社刊)を進呈します。セミナー当日、テキストとして使用いたします。
受講対象者
製品開発に従事する設計者・リーダークラス、調達・加工の担当者および品質・部品検査業務の担当者など
習得可能知識
1. 幾何公差の文法・用法の基礎と正しい使い方
2. 幾何公差の実用的な使い方と最新情報
3. 幾何公差表記と検査のノウハウ
概要
| 日時 | 2026年 4月 24日(金)10:00~17:00 (9:30 ログイン開始)※昼休憩1時間あり |
|---|---|
| 会場 | WEBセミナー WEBセミナーは、WEBミーティングツール「Zoom」を使用して開催いたします。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 ブラウザとインターネット接続環境があれば、どこからでも参加可能です。 |
| 受講料 | お一人様:48,400円(資料含む、消費税込) 受講にあたり |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 申込締切日について | 講座開催の3営業日前17:00〆切 ※セミナーによって締切が異なる場合もございます。早めにお申込みください。 原則、資料を受講者の方へ郵送するため、お手元に届く猶予を頂いております。予めご了承ください。 【営業日】について 営業日は平日になります。 ※土曜/日曜/祝祭日は、休業日です。 (例)6/16(火)開催の場合、6/11(木)が締切日となります。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
講師
プログラム
| 1 基礎編 |
| 1.1 設計意図を正しく伝える 1.1.1 図面と現物の相違 1.1.2 意図しない形になる原因とその対策 1.1.3 あいまいさのない形体定義 1.1.4 設計意図を正しく伝える方法 1.2 JIS製図には基本原則あり 1.2.1 モノの大きさと形の崩れの関係 1.2.2 独立の原則 1.2.3 最大実体と最小実体の基礎的事項 1.2.4 包絡の条件 1.3 基準を明確にする(データム) 1.3.1 基準とデータム 1.3.2 データム形体と実用データム形体 1.3.3 データムの優先順位と設計意図 1.3.4 共通データム 1.3.5 形体グループとデータム 1.3.6 データムターゲット 1.4 誤差のない寸法とは何か(TED) 1.4.1 TEDの基本定義 1.4.2 TEDのその他の用法 1.4.3 ISO規格によるTEDの定義 |
| 2 応用編 |
| 2.1 共通公差域で組立意図を伝える(付加記号その1) 2.1.1 指定記号の概要 2.1.2 共通公差域(CZ) 2.1.3 非同一平面への共通公差域指示 2.1.4 連続サイズ形体の公差(CT) 2.2 実際の使用状態を反映する(付加記号その2) 2.2.1 対象とする指定記号 2.2.2 突出公差域(Ⓟ) 2.2.3 自由状態(Ⓕ) 2.3 はめあい成立の条件を与える(付加記号その3) 2.3.1 はめあいの条件と問題点 2.3.2 はめあい成立のためのサイズ公差指示 2.3.3 はめあい成立のための幾何公差指示 2.3.4 はめあい成立のための複合した指示 2.4 組み立てばよしとする合理性(最大実体公差) 2.4.1 最大実体と最小実体 2.4.2 最大実体公差方式(Ⓜ) 2.4.3 機能ゲージ |
| 3 活用編 |
| 3.1 頻出の指示方法は定型化する(幾何公差の定石) 3.1.1 丸-長穴による位置決め 3.1.2 通し穴 3.2 幾何公差を正しく使う(幾何公差の間違い事例) 3.2.1 よくある間違い-文法編 3.2.2 よくある間違い-用法編 3.2.3 よくある間違い-番外編 3.3 グローバルな規格を理解しておく(ISO準拠の最新幾何公差定義) 3.3.1 幾何特性を厳密に定義する3つの記号 3.3.2 その他の指定記号 3.4 測れないものは作れない(幾何公差と測定) 3.4.1 幾何公差の測定 3.4.2 測定を考慮した幾何公差の選択 3.4.3 検査の効率化 |
| 4 まとめ |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |