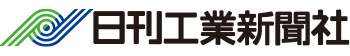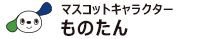セミナー
“なんとなく設計”からの脱却!
板金設計の標準化実践講座
材質・曲げ・接合の品質ばらつきと手戻りを防ぐ“板金設計標準化”ポイント
開催主旨
板金部品の設計現場では標準化が進んでおらず、個人の経験や感覚に依存した“なんとなく設計”が今も多く見られます。その結果、図面のばらつきや現場での迷い、不良・手戻りといった品質問題が繰り返されます。
標準化が進まない背景には、「現物を見ていない」「どうまとめればいいかわからない」「自社と他社では違う」という思い込みがあります。だからこそ今、設計者自身が現物を確認しながら“品質を支えるしくみ”としての標準化を見直すことが重要です。
この講座では、「板金設計の標準化=品質の再現性を確保する設計行為」と捉え、現物を用いながら、材質・曲げ・接合といった設計要素を実務の視点で整理します。そして、具体的に整理した方が良い項目なども示します。
対象は、カバーやブラケットなどの板金部品設計を担う技術者・技術管理者です。
(※プレス板金は対象外です)
現物を確認しながら、「感覚」ではなく「因果」で説明できる設計を目指し、最終的には自社で活用できる“板金設計標準の一覧化”へとつなげるための第一歩となる講座です。
受講対象者
・板金部品(カバー・ブラケット等)の設計を担当する実務設計者
・材質・曲げ・接合など、設計判断に迷いが多い若手〜中堅技術者
・図面のばらつきや現場とのすれ違いに課題を感じている設計部門リーダー
・社内で板金設計の標準化・教育を進めたい技術マネージャー
習得可能知識
・材質・曲げ・接合における設計判断のばらつきを抑え、部品の品質を安定させる
・現物と図面を照らし合わせながら設計を見る視点が養われ、加工現場とのズレを減らせる
・属人的な設計判断を言語化・構造化することで、社内の標準化や技術伝承の土台ができる
・接合や曲げ指示の不明確さによる現場手戻り・品質不良のリスクを減らせる
・「誰が設計してもどこで作っても同じ品質が再現できる」状態に近づき、
外注・内製の差を抑えた製品づくりが可能になる
概要
| 日時 | 2025年 11月 28日(金)13:30~16:30 (13:00 受付開始) |
|---|---|
| 会場 | 日刊工業新聞社 東京本社 セミナールーム ※会場には受講者用の駐車場が有りません。必ず最寄りの公共交通機関でご来場ください。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 |
| 受講料 | お一人様:29,700円(資料含む、消費税込) 受講にあたり |
| 定員 | 10名 |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社 東京本社
セミナールーム
中央区日本橋小網町14ー1
住生日本橋小網町ビル - セミナー会場案内図
プログラム
| 1. はじめに |
| ・本講座の目的と進め方の説明 ・なぜ今、板金設計の標準化が必要なのかを共有 |
| 2. なぜ標準化が必要か? |
| ・“なんとなく設計”が引き起こす品質のブレ ・「誰が設計しても、どこで作っても同じものができる」とは? ・図面のばらつきと現場トラブルの構造 |
| 3. 板金加工機と加工方法の整理 |
| ・切断:レーザ、タレパン、ニブラ、プラズマの特徴と適材適所 ・曲げ成形:プレスブレーキ、タレパン成形、プレス加工の違い ・接合:半自動、TIG、スポット、スタッド、レーザ、リベット、カシメなどの特徴と設計上の配慮点 |
| 4. 板金設計の標準化ポイント① 材質選定 |
| ・SPHC/SPCCなど鋼板材質の使い分けと特徴 ・「設計と材料の相性」の考え方 ・現場での実態(属人的な選定)とそのリスク ・板厚・表面処理・コストを踏まえた標準化 |
| 5. 板金設計の標準化ポイント② 曲げと展開 |
| ・完成部品と展開状態を見比べて形状変化を読み解く ・穴位置、最小曲げ高さ、逃げ加工などの影響 ・角R・曲げR・限界寸法など、形状設計の標準化 |
| 6. 板金設計の標準化ポイント③ 接合設計 |
| ・なぜ“良しなに接合”が危険なのか ・溶接・スナップ・ネジ留めの適用と使い分け ・すみ肉・つきあて・プラグ・片フランジ・スポットなど、各種溶接指示と現物との関係 ・ひずみの設計配慮 ・脚長・ビード長・ピッチ・本数などの溶接指示の標準化 |
| 7. まとめ・質疑応答 |
| ・板金設計における標準化の本質を再確認 ・現場と図面をつなぐ実践のヒント ・質疑応答 |