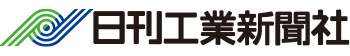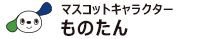セミナー
【ライブ配信&後日の録画視聴可】
トポロジー最適化の基礎から実践、
次世代設計への応用
~構造・熱・流体問題への実装・活用事例と
ジェネレーティブデザインの最新動向~
開催主旨
製品の性能を最大限に引き出す最適な形状をいかに見つけ出すか、これは、エンジニアリング設計における重要な課題です。本講座では、この課題を解決するトポロジー最適化の基礎理論を、数式に頼りすぎず、直感的かつ分かりやすく解説します。
基礎知識の解説に加え、構造、熱、流体といった多様な物理場における最新の応用事例を豊富に紹介。さらに、実践的な知識として、汎用ソフトウェアCOMSOL MultiphysicsとMATLABを組み合わせた実装手法を詳細に解説し、実務で即戦力となるスキルを習得していただきます。MATLABサンプルコードも提供するため、受講後すぐに自社の課題へ応用を試みることが可能です。
また、トポロジー最適化を基盤とし設計支援の最先端であるジェネレーティブデザインにも焦点を当て、トポロジー最適化が抱える本質的課題とその解決を目指すマルチフィデリティ形態創成法、さらには生成AIを利用したデータ駆動型アプローチの最新研究事例を紹介します。
最先端の設計技術を実務に取り入れたい方、そして次世代のエンジニアリングに挑戦したい方にとって、基礎理論から実践的な実装、そして革新的な設計手法の最新動向までを網羅した最適な内容となっています。
受講対象
■製品設計やエンジニアリングに携わり、設計の最適化・効率化を目指す技術者、研究者。
■トポロジー最適化やジェネレーティブデザインを実務や研究に導入・活用したい方。
■構造、熱、流体など、マルチフィジックス問題の最適形状探索に課題を感じている方。
■COMSOL MultiphysicsやMATLABを活用した実践的な最適化実装スキルを習得したい方。
■生成AIやデータ駆動型アプローチといった次世代の設計技術の最新動向に関心のある方。
習得可能知識
大学の工学系で習う微積分および線形代数を予備知識とします。
習得可能知識
■基礎理論と応用事例
・トポロジー最適化の基礎理論(密度法、フィルタリング、感度解析、数理計画法など。
・構造、熱、流体といった多様な物理場でのトポロジー最適化に関する最新の応用事例と、その実践的なノウハウ。
・トポロジー最適化の本質的課題と、その解決を目指すマルチフィデリティ形態創成法の基本的な考え方。
■実装スキルと実践ノウハウ
・汎用ソフトウェアCOMSOL MultiphysicsとMATLABを連携させた実践的なトポロジー最適化の実装手法。
・MATLABサンプルコードを活用し、熱伝導問題などを通じた最適化プロセスの具体的な実行手順。
・実務での課題に即座に応用するための、開発プラットフォームの構築と利用方法。
■次世代設計技術(ジェネレーティブデザイン)
・ジェネレーティブデザインの基本的な概念と、トポロジー最適化との関係性。
・生成AIやデータ駆動型の手法を利用した最先端のジェネレーティブデザインの枠組みと最新の研究事例(乱流熱伝達、機能と意匠の両立設計など)。
・次世代のエンジニアリング設計における技術の今後の展望。
本セミナーは、オンライン形式でのセミナーとなります。オンラインでのご視聴方法(参加用URL等)はご登録くださいましたメールにお知らせいたします。ZOOMでの視聴が困難な方には別途、こちらの手順を参照のうえブラウザ上でご視聴ください。
概要
| 日時 | 2026年 2月 24日(火)10:00~17:00 ※開催当日9:00まで申込受付 ※昼休憩は12:00~13:00を予定しています。 |
|---|---|
| 受講料 | 49,500円(テキスト代、録画視聴、税込、1名分) ※テキストはメールでお知らせします。 ※振込手数料は貴社でご負担願います。開催決定後、受講料の請求書(PDF)ををメールでお知らせします。 ※当日の参加が難しい方は録画での参加も可能です。録画での参加を希望される方は、申込フォームでご選択ください。 ※録画視聴は当日参加された方も講座終了後2週間にわたりご視聴いただけます。 |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 西日本支社 総合事業本部 セミナー係 TEL : 06-6946-3382 FAX : 06-6946-3389 E-mail : seminar-osaka@media.nikkan.co.jp |
| サンプルコードの実行例:熱流体トポロジー最適化(白:流体、黒:固体) |  |
講師
プログラム
|
1.トポロジー最適化の基礎(理論と応用事例) ※トポロジー最適化の歴史、基本的な考え方、そして応用範囲の広がりを理解します。 |
|
1-1 基本的な考え方 |
|
2.具体的な実装法(COMSOL/MATLAB連携による実践) オープンソースのコードと汎用ソフトウェアを組み合わせた、実践的な実装ノウハウをハンズオン形式で解説します。 (※講師によるデモを中心に進行し、ハンズオンは各自の環境での任意実習となります。実習の進め方やポイントは講師が解説します。) |
|
2-1 トポロジー最適化を実施するための様々なソフトウェア |
|
3.次世代ジェネレーティブデザインへの応用(最新動向) ※トポロジー最適化の限界を克服し、多様な設計案を自動生成する最新のデータ駆動型ジェネレーティブデザインを紹介します。 |
|
3-1 ジェネレーティブデザインの基本的な考え方 |
| 4.質疑応答 |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |