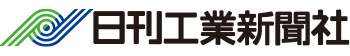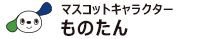セミナー
【ライブ配信&後日の録画視聴可】
ハイエントロピー合金の基礎・
作製・実用化に向けた研究開発事例
~実用化の鍵となる鋳造プロセスと、レアアース・レアメタル・貴金属低減を実現するカクテル効果の活用~
開催主旨
本講座では、特定の単一金属元素を中心とした従来の合金とは一線を画す、複数の主要元素からなる新素材「ハイエントロピー合金」について、その基礎から実用化に向けた最新の研究事例までを網羅します。
従来の合金は、鉄鋼のFeやアルミニウム合金のAlのように、特定の主要元素に少量の添加元素を加えて特性を調整する「足し算」の合金設計が主流でした。これに対し、ハイエントロピー合金(High-Entropy Alloys: HEAs)は、複数の元素をほぼ等しい割合で混ぜ合わせることで、エントロピーを極限まで増大させるあるいは極限まで大きくした合金から構成元素を減らして特定を調整する「引き算」の合金設計を行い、従来の合金にはない優れた特性を発現させる新しい材料群です。当初は5つ以上の元素を等原子組成で混合した単相固溶体(High-Entropy Alloys)が研究の中心でした。しかし、現在では単相に限定されず、低・中エントロピー合金や、金属間化合物、酸化物、セラミックスなどにも研究が広がっています。これらの新しい分類や、元素の多様性と不均一性が生み出す「4つのコア効果」(高エントロピー効果、格子歪み効果、遅延拡散効果、カクテル効果)に注目し、その特性発現メカニズムを掘り下げていきます。
特に、主要な作製方法の一つである鋳造法に注目し、既存の汎用的な鋳造設備を活用できるハイエントロピー鋳鉄や、高い強度と延性を両立する共晶ハイエントロピー合金など、実用化を視野に入れた具体的な研究開発事例を豊富に紹介します。これにより、研究室レベルの成果だけでなく、産業応用への道筋を明確に示します。また、生体材料、原子力材料、触媒といった機能材料分野への応用や、液体急冷プロセスを活用する積層造形(3Dプリンティング)との組み合わせについても言及し、ハイエントロピー合金が持つ広範な可能性と今後の展望を提示します。
本講座は、材料開発の新たなフロンティアに興味を持つ初心者の方から、実用化を目指す研究者や技術者まで、幅広い層の方にご理解いただける内容となっています。
受講対象
・材料開発に関わる方全般: 素材メーカー、部品メーカーの研究者、開発者、評価担当者など、ハイエントロピー合金の基礎から応用に関心のある方。
・金属・非金属材料の製造技術者: 鋳造、積層造形などのプロセス技術者で、新しい材料の製造プロセスに関心のある方。
・各産業分野の技術者・研究者:自身の専門分野における新素材の可能性を探求したい方。
※ ハイエントロピー合金の予備知識は必要ありません。初心者でも基礎から体系的に理解できる内容となっています。
習得可能知識
・ハイエントロピー合金の網羅的な理解を得ることができます。
・新しい合金設計の概念と独自の特性発現メカニズムを深く理解できます。
・鋳造法や積層造形といった主要な作製法に焦点を当てた研究事例を通して、道筋を明確にイメージできます。
・構造材料としての応用だけでなくハイエントロピー合金の持つ無限の可能性と、今後の研究・開発の方向性を把握できます。
本セミナーは、オンライン形式でのセミナーとなります。オンラインでのご視聴方法(参加用URL等)はご登録くださいましたメールにお知らせいたします。ZOOMでの視聴が困難な方には別途、こちらの手順を参照のうえブラウザ上でご視聴ください。
概要
| 日時 | 2026年 2月 27日(金)13:00~16:00 ※開催当日12:00まで申込受付 |
|---|---|
| 受講料 | 33,000円(テキスト代、録画視聴、税込、1名分) ※テキストはメールでお知らせします。 ※振込手数料は貴社でご負担願います。開催決定後、受講料の請求書(PDF)ををメールでお知らせします。 ※当日の参加が難しい方は録画での参加も可能です。録画での参加を希望される方は、申込フォームでご選択ください。 ※録画視聴は当日参加された方も講座終了後10日間にわたりご視聴いただけます。 |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 西日本支社 総合事業本部 セミナー係 TEL : 06-6946-3382 FAX : 06-6946-3389 E-mail : seminar-osaka@media.nikkan.co.jp |
講師
プログラム
| 1.ハイエントロピー合金の基礎概念 |
|
1-1 ハイエントロピー合金の定義と分類 |
| 2.ハイエントロピー合金の特性発現メカニズム |
|
2-1 エントロピーを増大させる意味 |
| 3.研究開発と実用化に向けた事例:(鋳造法を中心として) |
|
3-1 ハイエントロピースチールとハイエントロピー鋳鉄 |
|
4.まとめ・質疑応答 |
|
ハイエントロピー合金の今後の展望 |
|
【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |